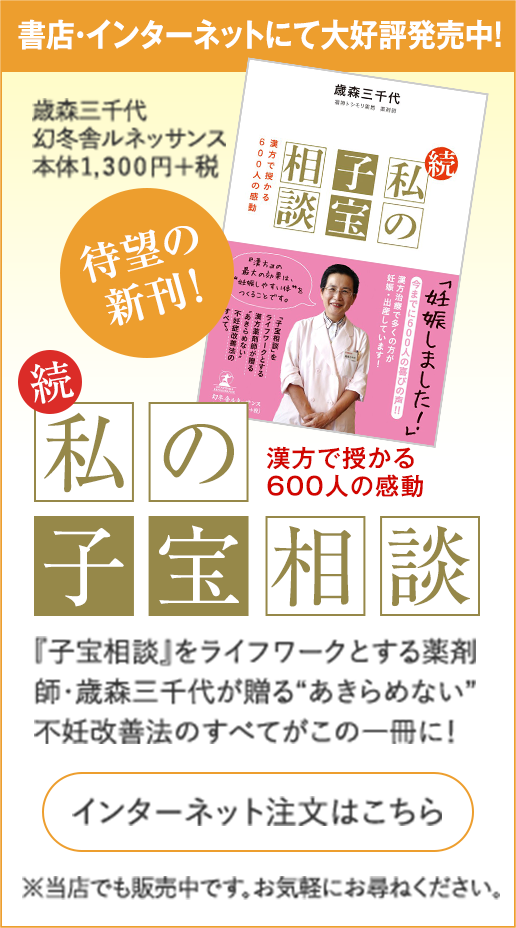帰脾湯と加味帰脾湯の違いとは?効果や副作用、使い分けを解説

帰脾湯と加味帰脾湯は、どちらも心身の疲れや不眠などに用いられる漢方薬ですが、名前が似ているため違いが分かりにくいと感じるかもしれません。
加味帰脾湯と帰脾湯の決定的な違いは、特定の生薬が追加されているかどうかであり、それによって効果や適した症状が異なります。
この記事では、帰脾湯と加味帰脾湯の違いを構成生薬や効能の観点から解説し、症状に合わせた選び方や副作用などの注意点を詳しく説明します。
帰脾湯と加味帰脾湯の決定的な違いは2つの生薬
帰脾湯と加味帰脾湯の最も大きな違いは、構成される生薬にあります。
加味帰脾湯は、帰脾湯の処方をベースに「柴胡(サイコ)」と「山梔子(サンシシ)」という2種類の生薬を加えたものです。
「加味」とは、漢方において主となる処方に生薬を加えて効果を調整することを意味します。
この追加された2つの生薬が、イライラやのぼせといった精神的な高ぶりや熱症状を鎮める働きを担っており、両者の効果の違いを生み出す重要な要素となっています。
構成生薬の違いを一覧で比較
帰脾湯は、人参や黄耆など12種類の生薬で構成されており、心身のエネルギー源である「気」と、全身に栄養を運ぶ「血」の両方を補う働きがあります。
一方、加味帰脾湯は、この帰脾湯の構成に柴胡と山梔子を加えた14種類の生薬から成り立っています。
これにより、気血を補う基本効果に加え、精神的な興奮や体内の熱を冷ます作用が強化されます。
似た働きを持つ漢方薬として、同じく気虚に用いる補中益気湯や、イライラを鎮める抑肝散、加味逍遙散などがありますが、それぞれ適応となる体質や症状が異なるため、使い分けが必要です。
効果・効能の違いを比較
帰脾湯は、主に消化器系の働きを助けて栄養の吸収を高め、血液を補うことで、心身の疲労や貧血、それに伴う精神不安や不眠といった症状を改善します。
漢方ではこれを「心脾両虚」の状態と呼びます。
対して加味帰脾湯は、帰脾湯が持つこれらの効能に加えて、柴胡と山梔子の作用によって、イライラや焦燥感、のぼせ、ほてりといった熱症状を鎮める効果が期待できます。
つまり、基本的な虚弱体質に、精神的な高ぶりや自律神経の乱れからくる熱感が伴う場合に、加味帰脾湯が選択されます。
帰脾湯とは?心身の疲労や貧血症状に用いられる漢方薬
帰脾湯は、胃腸の働きが弱って十分なエネルギー(気)や血液(血)が作れなくなり、心身に不調が現れた状態(気血両虚)に用いられる漢方薬です。
特に、思い悩みすぎることなどで心を消耗し、同時に消化器系の機能が低下している「心脾両虚」という状態を改善することを得意とします。
精神を安定させる作用と、消化吸収を助けて栄養を補う作用を併せ持ち、貧血や倦怠感、食欲不振、不安感、眠りが浅いといった症状の緩和に役立ちます。
帰脾湯が効果を発揮する主な症状
帰脾湯は虚弱体質で血色が悪く貧血気味な人のさまざまな症状に効果を発揮します。
具体的には精神的な疲れからくる不眠症不安感物忘れ食欲不振などが挙げられます。
身体的な症状としては全身の倦怠感、動悸、微熱、寝汗、月経不順や不正出血といった婦人科系のトラブルにも応用されます。
特に一つのことを考えすぎて堂々巡りになり、その結果として食事が喉を通らなかったり、夜になっても目が冴えて眠れなかったりするような場合に適しています。
医療用では1日量を2包や3包に分けて服用するのが一般的です。
帰脾湯の服用が向いている人の特徴
帰脾湯の服用が向いているのは、全体的に体力があまりなく、顔色が青白い、または黄色っぽいといった貧血傾向のある人です。
性格的には、繊細で真面目、物事を深く考え込んだり、くよくよと思い悩んだりしやすい傾向が見られます。
身体的な特徴としては、食が細く、胃腸が弱い、疲れやすいといった点が挙げられます。
漢方的な診察では、舌の色が白っぽく、脈が弱いことが多いのも特徴です。
ツムラをはじめとする各社から医療用医薬品として処方されるほか、市販もされており、心労がたたって身体が弱っていると感じる場合に適した処方です。
加味帰脾湯とは?精神不安やイライラも改善する漢方薬
加味帰脾湯は、帰脾湯の効果をベースに、精神的な興奮やイライラを鎮める作用を強化した漢方薬です。
帰脾湯が対応する気血不足による疲労や貧血、不安感といった症状に加えて、焦燥感や怒りっぽさ、のぼせ、ほてりといった「熱」の症状がみられる場合に用いられます。
追加された柴胡と山梔子が、自律神経系の高ぶりを鎮め、心身のバランスを整える働きをします。
そのため、心身ともに消耗しているものの、同時に精神的な高ぶりが抑えられない複雑な状態に適しています。
加味帰脾湯が効果を発揮する主な症状
加味帰脾湯は、帰脾湯と同様に貧血や不眠症、精神不安などに用いられますが、特にイライラや怒りっぽさを伴う場合に優れた効果を発揮します。
また、自律神経の乱れによって起こる、のぼせ、ほてり、微熱、寝汗といった症状にも対応します。
更年期障害や月経前症候群(PMS)などで見られる、気分の落ち込みとイライラの波、身体の熱感といった複合的な不調の緩和にも役立ちます。
心配事で眠れないだけでなく、焦る気持ちが高ぶって寝つけない、といったケースにも適しています。
その他、動悸や息切れ、神経症などにも応用されることがあります。
加味帰脾湯の服用が向いている人の特徴
加味帰脾湯が向いているのは、帰脾湯が適する虚弱体質や貧血傾向をベースに持ちながら、精神的に不安定でイライラしやすい人です。
些細なことでカッとなったり、焦燥感に駆られたりすることが多いのが特徴です。
身体的には、のぼせや顔のほてり、手のひらや足の裏が熱く感じるといった熱感を伴います。
また、胸のあたりが苦しく感じたり、寝汗をかいたりすることもあります。
考えすぎて疲れている一方で、神経は過敏になっているという、虚弱と興奮が入り混じった状態の人に最適な処方と言えます。
ストレスが多く、心身のバランスを崩しがちな現代人によく見られるタイプです。
【症状別】あなたに合うのはどっち?帰脾湯と加味帰脾湯の選び方
帰脾湯と加味帰脾湯は、どちらも心身の消耗に起因する不調に用いられますが、どちらを選ぶべきかは付随する症状によって決まります。
基本的な判断基準は、貧血や疲労といった「虚」の状態に、イライラやほてりといった「熱」や「興奮」の症状が加わっているかどうかです。
自分の心と体の状態をよく観察し、より合致する方を選ぶことが、効果的な改善への第一歩となります。
ここでは具体的な症状別に、それぞれの選び方を解説します。
精神的な不安や不眠で悩んでいる場合
精神的な不安や不眠は、両方の漢方薬が対象とする症状ですが、その質によって使い分けられます。
考え事や心配事が頭から離れず、くよくよと思い悩んで眠れない、あるいは眠りが浅いといった「静」のタイプの不眠には、心を落ち着かせ栄養を補う帰脾湯が適しています。
一方で、イライラや焦燥感が強く、神経が高ぶって寝つけない、あるいは怒りの感情で目が覚めてしまうような「動」のタイプの不眠には、興奮を鎮める作用が加わった加味帰脾湯が向いています。
不安の背景にある感情が、悲しみや憂いであれば帰脾湯、怒りや焦りであれば加味帰脾湯と考えると分かりやすいでしょう。
貧血や倦怠感が気になる場合
貧血や倦怠感は、エネルギー(気)と栄養(血)が不足している「気血両虚」の典型的な症状です。
これらの症状が主である場合は、まず帰脾湯が第一選択となります。
帰脾湯は、消化器系の働きを整えて食事からの栄養吸収を助け、血を補うことで、根本的な体力不足や貧血を改善する働きがあります。
立ちくらみや顔色の悪さ、少し動いただけですぐに疲れてしまうといった症状が中心であれば、帰脾湯を試してみるのがよいでしょう。
もしこれらの症状に加えて、理由のないイライラやのぼせを感じるようであれば、加味帰脾湯を検討します。
のぼせやイライラも同時に感じる場合
心身の疲労や貧血症状に加えて、のぼせやほてり、イライラといった症状がはっきりと現れている場合は、加味帰脾湯が適しています。
これらの症状は、体内の熱のバランスが崩れたり、自律神経が過敏になったりしているサインであり、加味帰脾湯に配合されている柴胡と山梔子が対応する領域です。
特に更年期や自律神経失調症などで、疲れやすいのにカッと頭に血が上る、不安で仕方ないのに些細なことで怒ってしまう、といった相反するような症状に悩まされている場合に効果的です。
虚弱体質と精神的な高ぶりが同時に見られるなら、加味帰脾湯が有力な選択肢となります。
帰脾湯・加味帰脾湯を服用する際の注意点
帰脾湯と加味帰脾湯は、体質に合えば心身の不調を和らげる助けとなりますが、医薬品であるため副作用や注意すべき点も存在します。
漢方薬は安全というイメージがあるかもしれませんが、すべての人に合うわけではありません。
服用を始める前には、起こりうる副作用や、医師への相談が必要なケース、他の薬との飲み合わせについて正しく理解しておくことが、安全な使用のために不可欠です。
ここでは、服用する前に知っておきたい注意点を具体的に説明します。
事前に知っておきたい副作用の症状
帰脾湯・加味帰脾湯の服用により、副作用が現れることがあります。
比較的起こりやすいものとして、食欲不振、胃部不快感、吐き気、腹痛、下痢といった消化器系の症状が報告されています。
また、皮膚に発疹やかゆみなどの過敏症状が出る可能性も考えられます。
頻度はまれですが、重大な副作用として「偽アルドステロン症」に注意が必要です。
これは、手足の脱力感やしびれ、こわばり、むくみ、血圧の上昇といった症状を引き起こします。
同様に、筋肉の痛みや脱力感を伴う「ミオパチー」が起こることもあります。
これらの初期症状に気づいた場合は、直ちに服用を中止して医師や薬剤師に相談してください。
服用前に医師への相談が必要なケース
特定の持病がある人や体調によっては、服用に際して慎重な判断が求められるため、事前に専門家への相談が必須です。
特に、高血圧、心臓病、腎臓病の診断を受けている人は、偽アルドステロン症のリスクが高まる可能性があるため、必ず医師に相談してください。
また、高齢者や、これまでに薬でアレルギー反応を起こした経験がある人も注意が必要です。
著しく胃腸が弱い人や、むくみの症状がある人も、服用前に医師、薬剤師、または登録販売者に伝えることが大切です。
妊娠中、または妊娠の可能性がある女性や授乳中の人も、自己判断での服用は避け、必ず専門家の指示を仰ぐようにしてください。
飲み合わせに注意が必要な薬
他の薬を服用している場合、飲み合わせによっては効果に影響が出たり、副作用のリスクが高まったりすることがあります。
帰脾湯と加味帰脾湯で特に注意が必要なのは、甘草(カンゾウ)という生薬を含む他の漢方薬との併用です。
甘草を過剰に摂取すると、偽アルドステロン症やミオパチーといった副作用が起こりやすくなります。
複数の漢方薬を服用する際には、成分が重複していないか必ず確認が必要です。
西洋薬との相互作用については、特に報告されているものは少ないですが、何らかの治療を受けている場合は、かかりつけの医師や薬剤師に漢方薬を服用したい旨を伝え、問題がないか確認することが安全です。
帰脾湯と加味帰脾湯に関するよくある質問
帰脾湯や加味帰脾湯の服用を検討するにあたり、効果が現れるまでの期間や購入方法、妊娠中・授乳中の使用など、さまざまな疑問が浮かぶことがあります。
これらの漢方薬をより安心して、かつ効果的に活用するためには、事前に具体的な疑問点を解消しておくことが重要です。
ここでは、多くの人が抱きがちな質問とその回答をまとめました。
実際に服用を始める前の参考として、ぜひ確認してください。
効果はどのくらいの期間で実感できますか?
漢方薬の効果が現れるまでの期間は、その人の体質や症状の重さ、生活習慣などによって大きく異なり、一概には言えません。
一般的には、2週間から1ヶ月程度の服用を続けることで、何らかの体調の変化を感じ始めることが多いとされています。
不眠などの精神的な症状は比較的早めに、貧血や倦怠感といった体質に関わる慢性的な症状は、改善を実感するまでにもう少し時間がかかる傾向があります。
もし1ヶ月以上服用しても全く改善が見られない場合は、処方が体質に合っていない可能性も考えられるため、処方を受けた医師や薬剤師に相談することをおすすめします。
市販薬は購入できますか?
帰脾湯と加味帰脾湯は、医師から処方される医療用医薬品のほかに、薬局やドラッグストアなどで購入できる市販薬(一般用医薬品)としても販売されています。
そのため、比較的軽い症状であれば、専門家の診察を受けずに試すことも可能です。
ただし、市販薬は医療用に比べて生薬の含有量が調整されている場合があるため、効能・効果や用法・用量を製品のパッケージでよく確認してください。
どの製品を選べばよいか迷う場合や、複数の症状が重なっている場合は、自己判断で購入する前に、薬局の薬剤師や登録販売者に相談すると、より適切なアドバイスが受けられます。
妊娠中や授乳中でも服用できますか?
妊娠中や授乳中の漢方薬の服用については、自己判断で行うことは絶対に避けるべきです。
妊娠中の服用に関しては、治療上の有益性が危険性を上回ると医師が判断した場合にのみ処方されます。
一部の生薬が胎児や母体に影響を与える可能性を完全に否定できないため、非常に慎重な判断が求められます。
授乳中についても同様で、生薬の成分が母乳に移行する可能性を考慮しなくてはなりません。
産後の不調などで服用を希望する場合は、必ずかかりつけの産婦人科医や漢方に詳しい医師に相談し、安全性を確認した上で指示に従うようにしてください。
まとめ
帰脾湯と加味帰脾湯の主な違いは、イライラやほてりといった熱症状に対応する柴胡と山梔子の有無にあります。
心身の疲労や貧血、くよくよ悩むタイプの不眠には帰脾湯が、これらの症状に加えて精神的な高ぶりやのぼせが顕著な場合には加味帰脾湯が適しています。
どちらの漢方薬も、心と体の両面に働きかける優れた処方ですが、効果を最大限に引き出すには、自分の現在の症状や体質を正しく見極めることが重要です。
服用に際しては副作用のリスクも考慮し、不安な点や持病がある場合は、医師や薬剤師などの専門家に相談の上で、適切に活用してください。