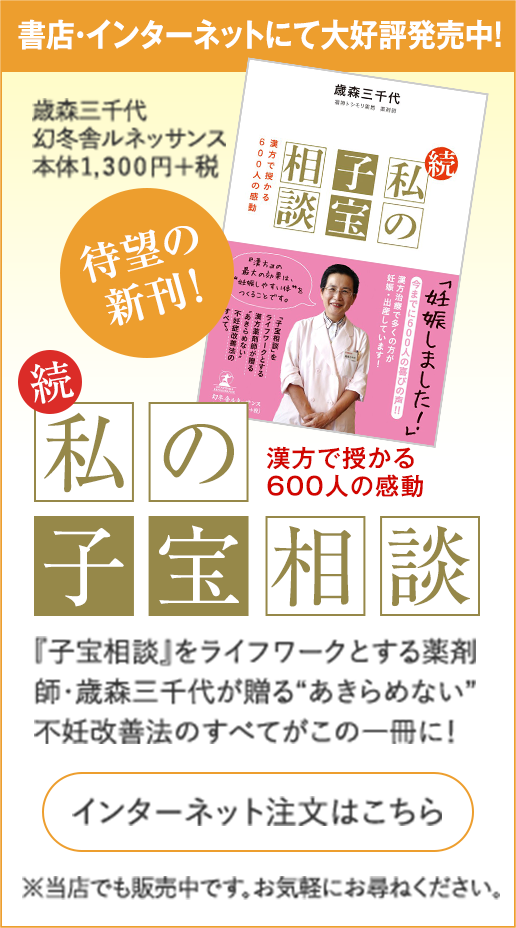慢性下痢におすすめの市販漢方薬|原因・タイプ別の選び方を解説
 漢方
漢方
長引くお腹の不調である慢性的な下痢は、日常生活の質を大きく低下させる要因となります。
西洋薬による治療で改善が見られない場合、体質から見直す漢方薬が有効な選択肢になることがあります。
この記事では、慢性的な下痢が起こる原因を漢方の視点から解説し、それぞれの症状や体質に合わせた市販の漢方薬の選び方を紹介します。
つらい慢性下痢の改善に漢方薬が選ばれる理由
慢性的な下痢に対して漢方薬が選択されるのは、症状を直接的に抑えるだけでなく、下痢が起こる根本的な原因に働きかけるためです。
漢方では、体の機能のバランスが崩れることで不調が生じると考え、一人ひとりの体質や症状に合わせて処方を選びます。
消化機能の低下、冷え、ストレスなど、慢性的な下痢の背景にある体質的な問題を整えることで、症状の根本的な改善を目指します。
あなたの慢性下痢はどのタイプ?漢方で考える3つの原因
漢方では、慢性的な下痢を一つの症状として捉えるのではなく、その人の体質や生活習慣から根本的な原因を探ります。
主な原因として「ストレスや緊張による腸の過敏」「胃腸の冷えによる消化機能の低下」「体内の水分バランスの乱れ」の3つのタイプが挙げられます。
自身の慢性的な下痢がどのタイプに該当するかを把握することが、適切な漢方薬を選ぶための第一歩となります。
ストレスや緊張による腸の過敏
精神的なストレスや緊張は自律神経のバランスを乱し、腸の動きを過敏にさせることがあります。
漢方では、感情のコントロールに関わる「肝(かん)」の機能が乱れると、消化吸収を担う「脾(ひ)」に悪影響を及ぼし、下痢を引き起こすと考えます。
これは「肝脾不和(かんぴふわ)」と呼ばれる状態です。
特に、通勤前や試験前などプレッシャーがかかる場面で腹痛を伴う下痢が起こりやすく、便秘と下痢を交互に繰り返すことも特徴です。
お腹の張りやガスの発生を伴う場合も少なくありません。
このようなタイプの慢性的な下痢には、気の巡りを改善して高ぶった神経を鎮め、腸の機能を正常化させるアプローチが用いられます。
胃腸の冷えによる消化機能の低下
体、特にお腹周りが冷えることで胃腸の働きが鈍り、消化不良による下痢が起こりやすくなります。
漢方では、体を温めるエネルギーである「陽気」が不足した「脾陽虚(ひようきょ)」という状態と捉えます。
このタイプは、冷たい飲み物や食べ物を摂取した後に症状が悪化する傾向があります。
慢性的な下痢に加えて、食欲不振や胃もたれ、全身の倦怠感、手足の冷えなどを伴うことも少なくありません。
便に消化されていない食べ物が混じっている(未消化便)のも特徴の一つです。
胃腸そのものが弱っているため、体を内側から温めて消化吸収機能を助けることで、慢性的な下痢の改善を目指します。
体内の水分バランスの乱れ
体内の水分代謝が滞り、余分な水分が胃腸に溜まることも慢性的な下痢の原因となります。
これを漢方では「水滞(すいたい)」や「水毒(すいどく)」と呼びます。
このタイプの下痢は、水のような便(水様便)が特徴で、お腹がゴロゴロと鳴ったり、お腹を叩くとポチャポチャと音がしたりします。
下痢だけでなく、顔や手足のむくみ、めまい、頭痛、乗り物酔いしやすいといった症状を伴うこともあります。
特に湿度の高い季節や、冷たい飲み物の過剰摂取によって症状が悪化しやすい傾向が見られます。
この場合、体内の水分循環を整え、余分な水分を尿として排出させる「利水作用」を持つ漢方薬を用いて、胃腸の負担を軽減し下痢を改善します。
【症状・体質別】自分に合った市販漢方薬の選び方
ここでは、先に解説した3つの原因タイプ別に、薬局やドラッグストアなどで購入できる代表的な市販の漢方薬を紹介します。
自分の症状や体質がどのタイプに近いかを考え、それぞれの漢方薬の特徴を参考に選ぶことが大切です。
市販薬を選ぶ際は、パッケージに記載されている効能・効果や「体力中等度」などの記載を確認し、自分の状態に合ったものを見つけるようにしてください。
ストレスやプレッシャーで腹痛を伴う下痢が起こる方向けの漢方薬
ストレスが原因の下痢には、気の巡りを整え、腸の緊張を和らげる漢方薬が適しています。
代表的な処方として「桂枝加芍薬湯(けいしかしゃくやくとう)」が挙げられます。
この漢方薬は、お腹の張りや腹痛を伴う下痢、または便秘と下痢を繰り返すような症状に用いられ、過敏になった腸の動きを穏やかにします。
比較的体力が虚弱な人に向いています。
また、「半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)」も選択肢の一つです。
みぞおちのつかえ感や食欲不振、口内炎などを伴う場合の神経性の胃腸炎や下痢に効果が期待できます。
ストレスによる胃腸機能の乱れを整え、心身の両面から症状の改善に導きます。
お腹の冷えや胃腸の弱さが原因で慢性下痢になる方向けの漢方薬
胃腸が冷えて機能が低下しているタイプには、お腹を温めて消化吸収を助ける漢方薬が用いられます。
代表的な処方は「人参湯(にんじんとう)」です。
体力がなく、手足や胃腸が冷えやすく、食欲不振や疲れやすさを伴う慢性的な下痢に適しています。
胃腸を内側から温め、消化機能を高めることで症状を和らげます。
さらに冷えが強く、めまいや強い倦怠感、むくみなどを伴う場合には「真武湯(しんぶとう)」が選択されます。
新陳代謝の低下した人の下痢に用いられ、体を温める作用がより強力です。
これらの漢方薬は、弱った胃腸の働きを根本から立て直し、冷えにくい体質へと導くことを目指します。
水のような下痢が特徴で、むくみやすい方向けの漢方薬
体内の水分バランスの乱れが原因で起こる水様性の下痢には、水分代謝を整える「利水作用」のある漢方薬が有効です。
代表的な処方に「五苓散(ごれいさん)」があります。
この漢方薬は、体内の余分な水分を尿として排出させることで、水様性の下痢やむくみ、めまいなどを改善します。
のどの渇きや尿量の減少が使用の目安です。
また、食あたりや吐き気、腹痛などを伴う場合は、「五苓散」に消化を助ける作用を加えた「胃苓湯(いれいとう)」が適しています。
夏場の冷たい飲食物の摂りすぎによる下痢や、吐き気を伴う胃腸炎などにも用いられ、乱れた水分代謝と消化機能の両方を整えます。
市販の漢方薬を服用する前に知っておきたい注意点
市販の漢方薬は手軽に利用できますが、医薬品であるため、安全かつ効果的に使用するための注意点があります。
漢方薬にも副作用や他の薬との飲み合わせのリスクが存在し、服用のタイミングや食生活も効果に影響を与えます。
服用を始める前にこれらのポイントを理解しておくことで、より安心してセルフケアに取り組めます。
副作用が起こる可能性や薬の飲み合わせ
漢方薬は天然の生薬を原料としていますが、医薬品である以上、副作用のリスクは存在します。
体質に合わない場合、皮膚の発疹やかゆみ、食欲不振、胃の不快感などの症状が現れることがあります。
特に、多くの漢方薬に含まれる甘草(カンゾウ)という生薬の過剰摂取により、むくみや血圧上昇などを引き起こす「偽アルドステロン症」という副作用が起こる可能性も指摘されています。
また、他の薬を服用している場合は注意が必要です。
複数の漢方薬を同時に服用すると特定の生薬成分が重複したり、西洋薬との間で相互作用を起こしたりする恐れがあります。
購入時には、現在服用中の薬を薬剤師や登録販売者に伝え、飲み合わせに問題がないか必ず確認してください。
漢方の効果を高める服用のタイミング
漢方薬の効果を最大限に引き出すためには、適切なタイミングで服用することが重要です。
一般的に、漢方薬は「食前(食事の約30分前)」または「食間(食後約2時間後)」の空腹時に服用することが推奨されます。
これは、胃に食べ物が入っていない状態の方が、生薬の有効成分が効率的に吸収されやすいと考えられているためです。
飲み忘れた場合は、気づいた時点で服用して構いませんが、次の服用時間が近い場合は1回分を飛ばしてください。
ただし、漢方薬の種類や個人の胃腸の状態によっては、食後の服用が指示されることもあります。
胃が弱いなどで空腹時の服用が難しい場合は、薬剤師や登録販売者に相談すると良いでしょう。
漢方と合わせて改善したい食生活のポイント
慢性的な下痢の改善には、漢方薬の服用と並行して日々の食生活を見直すことが欠かせません。
まず、胃腸を冷やして消化機能を低下させる冷たい飲み物や食べ物は避け、なるべく温かいものを摂るように心がけます。
特に、胃腸の冷えが原因となっている場合は効果的です。
また、一度にたくさん食べる暴飲暴食や、腸を刺激する脂っこい食事、香辛料の多い料理は、胃腸に大きな負担をかけるため控えるべきです。
食事は、おかゆやうどん、豆腐、白身魚など、消化が良く栄養のあるものを選び、ゆっくりよく噛んで食べることを意識します。
特に鍋料理は、栄養素をバランスよく食べやすく、オススメです。
生活習慣全体を見直し、漢方薬の働きを助けることで、より根本的な体質改善が期待できます。
まとめ
慢性的な下痢の改善において、漢方薬は症状の根本にある体質の乱れを整えるという考え方に基づきます。
下痢の原因は一様ではなく、ストレスによる腸の過敏性、胃腸の冷えによる機能低下、体内の水分代謝の不調など、個々の状態によって異なります。
市販の漢方薬を選ぶ際には、これらの原因のうち、自分の症状や体質に最も近いものに対応する処方を選択することが求められます。
服用前には、副作用や飲み合わせに関する注意点を確認し、食生活の改善も並行して行うとより効果的です。
なお、症状が改善しない場合や、他の疾患が疑われる場合は、自己判断を続けずに医療機関で診察を受けてください。