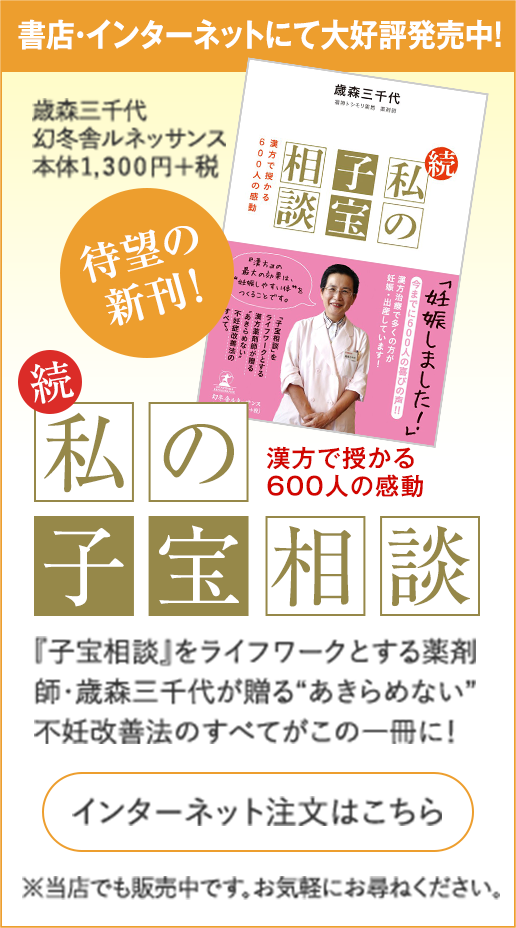変形性膝関節症(膝の痛み)におすすめの漢方薬|薬剤師が症状別の選び方を解説
 漢方
漢方
市販の鎮痛薬や湿布ではなかなか改善しない膝の痛みに対し、漢方薬は体質からアプローチすることで根本的な改善を目指します。
漢方医学では、膝の痛みを単なる局所的な問題としてではなく、「気・血・水」のバランスの乱れと捉えます。
この記事では、ご自身の症状や体質に合った漢方薬の選び方を、薬剤師が分かりやすく解説します。
自分に合う漢方薬を見つけ、つらい膝の痛みの緩和にお役立てください。
はじめに|膝の痛みに漢方薬がアプローチする仕組みとは
漢方医学では、膝が痛い状態を体全体のバランスの乱れが原因で起こると考えます。
具体的には、生命エネルギーである「気(き)」、血液とその働きを指す「血(けつ)」、血液以外の体液である「水(すい)」の3つが体内をスムーズに巡ることで健康が保たれているとされます。
これらの流れが滞ったり、不足したりすることで、膝に痛みや腫れ、水が溜まるといった症状が現れるのです。
漢方薬は、この「気・血・水」のバランスを整え、体質を根本から改善することで、膝の痛みを和らげることを目的とします。
あなたの膝痛はどのタイプ?体質と症状から選ぶ3つのポイント
自分に適した漢方薬を見つけるためには、まず自分の膝の痛みがどのタイプに当てはまるかを知ることが重要です。
漢方では、痛みの原因を特定するために、症状の現れ方や体質を詳しく見ていきます。
ここでは、膝の状態、痛みが悪化する状況、そして全身の体力や血行という3つのポイントから、ご自身のタイプを見極める方法を解説します。
特に、ホルモンバランスが変化する更年期以降は、これらの不調が顕著に現れることがあります。
ポイント1:膝に水が溜まり、腫れやむくみがあるか確認する
膝の痛みとともに、腫れぼったさやむくみを感じる場合、漢方では体内の水分代謝が滞っている「水滞(すいたい)」の状態と考えます。
膝関節に水が溜まる、いわゆる「膝に水が溜まった」状態もこれにあたります。
このタイプの特徴は、膝が重だるく、曲げ伸ばしがしにくい感覚を伴うことです。
また、体全体がむくみやすかったり、天候が悪い日に症状が悪化したりする傾向が見られます。
このような症状がある場合は、体内の余分な「水」を排出し、水分代謝を整える作用のある漢方薬が適しています。
まずはご自身の膝を触って、熱感や腫れの有無を確認してみてください。
ポイント2:冷えや湿気など、痛みが悪化する状況を把握する
膝の痛みが特定の状況で強くなる場合、その状況が痛みの原因を探る重要な手がかりとなります。
例えば、寒い日や冷房の効いた部屋にいると痛みがズキズキと増すのであれば、体の冷えが原因である「寒邪(かんじゃ)」が影響している可能性があります。
一方で、雨の日や湿度が高い日に膝が重だるく痛む場合は、体内に余分な湿気が溜まっている「湿邪(しつじゃ)」が原因と考えられます。
このように、痛みが悪化する環境や時間帯(例:朝方、夜間)を把握することで、体を温めるべきか、湿気を取り除くべきかなど、漢方薬を選ぶ上での方針が定まります。
ポイント3:体力や血行の状態から根本的な原因を探る
膝の痛みは、全身の健康状態と密接に関わっています。
例えば、普段から疲れやすく体力に自信がない「気虚(ききょ)」タイプの人は、体を支えるエネルギーが不足し、関節に負担がかかりやすくなっています。
また、血行が悪く、手足のしびれや肩こり、腰痛などを伴う場合は、「瘀血(おけつ)」という血の巡りが滞った状態が痛みの原因かもしれません。
瘀血による痛みは、チクチクと刺すような痛みが特徴で、夜間に悪化しやすい傾向があります。
このように、膝だけでなく全身の状態を総合的に見ることで、痛みの根本的な原因を突き止め、より体質に合った漢方薬を選ぶことができます。
【症状・体質別】薬剤師が選ぶ膝痛におすすめの漢方薬
ここでは、前述した体質や症状のタイプ別に、膝の痛みに用いられる代表的な漢方薬を紹介します。
漢方薬は、クラシエやツムラといった製薬会社が作り、病院を受診して処方箋で出してもらう医療用医薬品だけでなく、漢方薬局やドラッグストアなどで購入できる一般用医薬品としても販売されています。
ご自身の症状と照らし合わせながら、どの漢方薬が合いそうか、選ぶ際の参考にしてください。
ただし、最適な漢方薬は、個々の体質によって異なるため、専門家への相談が推奨されます。
防已黄耆湯(ぼういおうぎとう):水が溜まりやすく、むくみがちな膝の痛みに
防已黄耆湯は、体力が中等度以下で疲れやすく、汗をかきやすい傾向のある人に適した漢方薬です。
特に、体内の水分代謝を改善する働きに優れており、膝に水が溜まって腫れぼったい、むくみが気になるといった症状に用いられます。
漢方でいう「水滞」の状態を改善し、余分な「水」を排出することで、関節の腫れや重だるい痛みを和らげます。
色白で筋肉が柔らかく、いわゆる水太り体質の方の、多汗症や肥満に伴う関節の腫れや痛みにも効果が期待できます。
普段からむくみやすく、疲れが溜まると膝が痛むという方におすすめの漢方薬です。
桂枝加朮附湯(けいしかじゅつぶとう):体の冷えが原因でズキズキ痛む膝に
桂枝加朮附湯は、体力が虚弱で、特に冷えが強い方の関節痛や神経痛に用いられる漢方薬です。
冷えに対して役立つ附子が配合されており、寒さやクーラーなどで悪化する膝の痛みに適しています。
手足の末端が冷えやすく、温めると痛みが和らぐという特徴を持つ方に選ばれることが多いです。
加齢や更年期などで体が冷えやすくなった方の膝痛にも応用されます。
血行を促進し、体の中から温めることで、冷えからくるズキズキとした痛みを緩和する効果が期待できます。
汗が出やすく、尿量が少ないという傾向も、この漢方薬を選ぶ際の目安となります。
薏苡仁湯(よくいにんとう):雨の日など湿気で悪化する関節の重だるい痛みに
薏苡仁湯は、関節に熱感や腫れがあり、特に雨の日や湿度の高い環境で症状が悪化する方に適した漢方薬です。
体内の余分な水分である「湿」を取り除く作用があり、湿気によって引き起こされる重だるい痛みや、関節のむくみを改善します。
筋肉のけいれんやこわばりを伴う痛みにも用いられることがあります。
比較的体力があり、関節リウマチや神経痛などで、熱感や腫れ、痛みが慢性的に続いている場合に選択されることが多い漢方薬です。
梅雨の時期になると決まって膝が痛む、という方はこの漢方薬が合う可能性があります。
疎経活血湯(そけいかっけつとう):血行不良によるしびれを伴う膝の痛みに
疎経活血湯は、血行不良、すなわち「瘀血」が原因で起こる痛みに用いられる漢方薬です。
痛みとともに、しびれや重だるさを感じる場合に適しています。
特に、夜間に痛みが強くなる、痛む場所が移動するといった特徴が見られる際に選ばれます。
この漢方薬は、滞った血の流れをスムーズにし、体内の水分の巡りも整えることで、筋肉や関節の痛みを和らげます。
中年期以降の方で、慢性的な腰痛や筋肉痛を伴う膝の痛みに悩んでいる場合に効果が期待できる漢方薬です。
血行を促進し、痛みやしびれを根本から改善することを目指します。
麻杏薏甘湯(まきょうよっかんとう):関節や筋肉に熱感や腫れ、痛みを伴う場合に
麻杏薏甘湯は、比較的体力があり、関節や筋肉に熱感や腫れ、痛みを伴う場合に用いられる漢方薬です。
炎症を抑え、痛みを取り除く作用に優れているため、特に急性の関節炎や、日中の活動によって痛みが増すようなタイプの膝痛に適しています。
主成分である麻黄と薏苡仁は、発汗を促し、体内の余分な水分を排出することで、関節の腫れや痛みを和らげます。
また、神経痛や筋肉痛、いぼにも効果があるとされています。
風邪の後に関節が痛みだした場合や、運動後の筋肉痛のような症状にも応用されることがあります。
五積散(ごしゃくさん):下半身の冷えが強く、腰から足にかけての重だるい痛みに
五積散は、冷えと湿気が原因で起こる様々な不調に用いられる漢方薬です。
漢方の考え方である「気・血・水」のうち、気滞・血瘀・痰湿・寒邪・食積という五つの滞りすべてに対応することからこの名がついています。
胃腸が弱く、冷え性で、頭痛や腰痛、関節痛など、全身にわたる不調を抱えている人に適しています。
特に、下半身の冷えが強く、腰から足にかけて重だるい痛みがある場合の膝痛に効果が期待できます。
体を温めながら水分代謝を整え、血行を促進することで、複雑な原因が絡み合った慢性的な痛みを和らげることを目指す漢方薬です。
漢方薬を服用する前に知っておきたい注意点
漢方薬は天然の生薬から作られているため、体に優しいというイメージがありますが、医薬品であることに変わりはありません。
そのため、服用する際にはいくつかの注意点があります。
自分の体質や症状に合わない漢方薬を選ぶと、期待した効果が得られないばかりか、副作用が現れる可能性も考えられます。
服用を開始する前には、医師や薬剤師などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。
漢方薬にも副作用はある?服用前に確認すべきこと
漢方薬にも副作用のリスクは存在します。
よく見られるものとしては、食欲不振、胃の不快感、下痢、便秘などの消化器症状や、発疹、かゆみといった皮膚症状が挙げられます。
また、まれではありますが、間質性肺炎や肝機能障害などの重篤な副作用が起こる可能性もあります。
特に、複数の漢方薬を服用している場合、甘草(カンゾウ)という生薬が重複し、偽アルドステロン症(むくみ、高血圧、低カリウム血症など)を引き起こすことがあるため注意が必要です。
ご自身で、市販のツムラ漢方、クラシエ漢方などの製品を購入する際は、必ず添付文書をよく読み、含まれている生薬や副作用について確認してください。
長期間服用しても改善しない場合は医療機関の受診を検討しよう
漢方薬は体質をゆっくりと改善していくものが多いため、効果を実感するまでにある程度の時間が必要な場合があります。
しかし、一般的に1ヶ月程度服用を続けても症状の改善が全く見られない、あるいはかえって症状が悪化するようであれば、その漢方薬が体質に合っていない可能性が高いです。
また、膝の痛みの原因が、単なる加齢によるものではなく、変形性膝関節症が進行している、あるいは他の病気が隠れているというケースも考えられます。
自己判断で服用を続けることはせず、整形外科などの専門の医療機関を受診して、正確な診断を受けることが重要です。
漢方の効果を高めるために|日常生活でできる膝痛セルフケア
漢方薬の効果を最大限に引き出すためには、薬の服用と並行して生活習慣を見直すことが欠かせません。
食事や運動、日々の動作の工夫など、セルフケアを積極的に取り入れることで、痛みの根本原因にアプローチし、症状の改善を早めることが期待できます。
ここでは、漢方医学的な視点も取り入れながら、日常生活で簡単に実践できる膝痛のセルフケア方法を紹介します。
継続的なケアが、再発予防にもつながります。
食生活を見直して体を内側から温める
漢方では、体の冷えは「気」や「血」の巡りを悪くし、痛みを引き起こす大きな原因と考えられています。
そのため、食生活において体を内側から温める工夫をすることが、膝痛の緩和に役立ちます。
具体的には、ネギ、ショウガ、ニンニク、ニラといった香味野菜や、カボチャ、ゴボウなどの根菜類を積極的に食事に取り入れると良いでしょう。
逆に、生野菜や果物、冷たい飲み物、白砂糖を多く含む食品は体を冷やす性質があるため、摂取を控えめにすることが望ましいです。
クラシエなどの漢方メーカーのサイトでも、食養生に関する情報が発信されていますので、参考にしながらバランスの取れた温かい食事を心がけてください。
適度な運動で膝周りの筋力をサポートする
膝の痛みを恐れて動かさないでいると、膝を支える筋力が低下し、かえって関節が不安定になり痛みが悪化する悪循環に陥ることがあります。
痛みが出ない範囲で適度な運動を行い、膝周りの筋肉、特に太ももの前側にある大腿四頭筋を鍛えることが重要です。
この筋肉は膝関節にかかる負担を軽減するクッションの役割を果たします。
椅子に座った状態で片足をゆっくりと上げて下ろす運動や、プールでの水中ウォーキングなど、膝への負担が少ない運動から始めるのがおすすめです。
無理のない範囲で継続し、筋力の維持・向上を目指しましょう。
サポーターを活用して膝への負担を軽減する
痛みが強い時や、長時間歩く必要がある場合には、膝用のサポーターを活用するのも有効な手段です。
サポーターを装着することで、膝関節が安定し、歩行時の衝撃を和らげることができます。
また、保温効果のあるサポーターは、冷えによる痛みの緩和にも役立ちます。
ただし、常にサポーターに頼りすぎると、膝周りの筋肉が弱ってしまう可能性も指摘されています。
そのため、頼りきりになるのではなく、あくまで補助的なものとして使用するのが良いでしょう。
痛みが強い日や、スポーツをする際など、必要な場面で適切に活用し、膝への負担をコントロールすることが求められます。
まとめ
膝が痛いという症状に対して、漢方薬は痛みそのものを抑えるだけでなく、痛みの原因となっている体質を根本から改善することを目指す治療法です。
ご自身の膝の痛みが、体内の水分代謝の乱れ、冷え、血行不良など、どのタイプに起因するのかを把握することが、適切な漢方薬選びの第一歩となります。
本記事で紹介した漢方薬はあくまで一例であり、最適な漢方薬は、一人ひとりの体質や症状の詳細によって異なります。
漢方薬の服用を考える際は、自己判断で選ぶのではなく、医師、薬剤師、または登録販売者といった専門家に必ず相談してください。
日々のセルフケアと合わせて、自分に合った漢方薬を取り入れ、つらい膝の痛みの改善を目指しましょう。