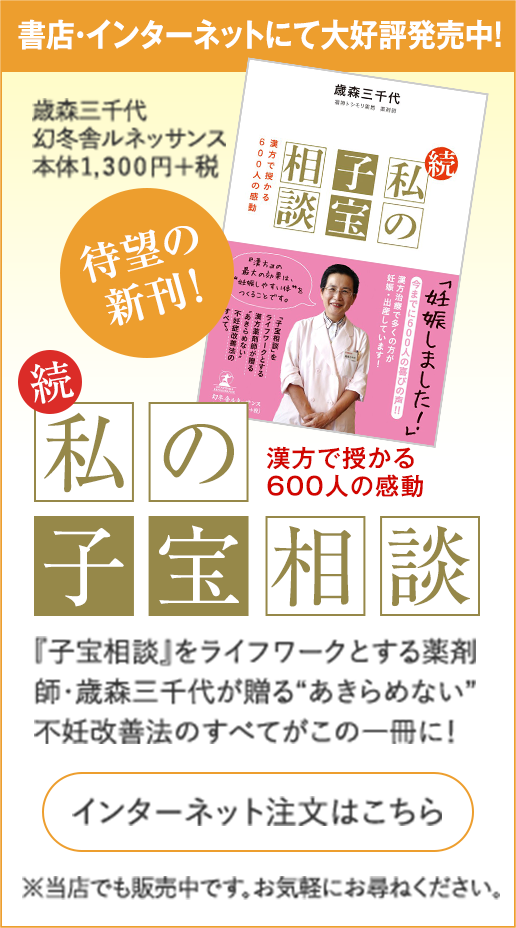後鼻漏の漢方薬|症状・体質別の薬の選び方を解説【薬局で買える】
 漢方
漢方
後鼻漏の不快な症状を和らげるため、漢方薬の服用を検討する方が増えています。
この記事では、後鼻漏の漢方薬に関心がある方へ向けて、症状や体質に合わせた漢方薬の選び方を解説します。
薬局で手軽に購入できる市販の薬を中心に、おすすめの処方を紹介し、セルフケアでできる対策もあわせて説明します。
自分に合った漢方を見つけ、つらい症状の改善を目指しましょう。
後鼻漏とは?喉の奥に鼻水が垂れる不快な症状
後鼻漏は、鼻水が鼻の前から出るのではなく、喉の奥へと流れ落ちる症状を指します。
通常、鼻水は無意識のうちに飲み込んでいますが、量が増えたり粘り気が強くなったりすると、喉に鼻水が垂れる感覚や喉の違和感として自覚されます。
この流れ落ちた鼻水や痰が喉に絡むことで、頻繁な咳払いや咳、痰の原因になることも少なくありません。
就寝中に症状が現れやすく、睡眠の妨げになる場合もあります。
後鼻漏を引き起こす主な原因
後鼻漏は、鼻や喉の粘膜に異常が生じるさまざまな疾患が原因で起こります。
代表的な原因として、アレルギー反応によって鼻水が過剰に分泌されるアレルギー性鼻炎や花粉症が挙げられます。
また、細菌やウイルスの感染によって鼻の奥にある副鼻腔が炎症を起こす副鼻腔炎(蓄膿症)では、粘り気の強い鼻水が喉に流れやすくなります。
その他、慢性鼻炎や風邪、喉の奥にある上咽頭炎も原因となり得ます。
体質的な要因やストレスが自律神経のバランスを崩し、症状を悪化させることもあります。
なぜ後鼻漏に漢方が使われるのか?体質から改善する考え方
西洋医学が症状を直接抑えることを主眼に置くのに対し、後鼻漏と漢方の関わり方では、症状が起こる根本的な原因、つまり体質の改善を目指します。
漢方では、後鼻漏を体内の水分バランスの乱れである「水滞(すいたい)」や、体の「冷え」が原因で起こると捉えることが多いです。
特に胃腸の機能が低下すると、水分代謝が滞り、余分な水分が鼻水としてあふれ出ると考えます。
そのため、体を温めたり、胃の働きを整えたりする漢方薬を用いることで、鼻水の過剰な分泌を抑制し、後鼻漏の改善に効果が期待できます。
【症状・体質別】薬局で買える後鼻漏におすすめの漢方薬
後鼻漏に効く漢方薬は一種類ではなく、個々の症状や体質に合わせて選ぶことが重要です。
例えば、鼻水がサラサラしているかネバネバしているか、色は透明か黄色か、鼻づまりや咳、喉の乾燥といった他の症状を伴うかによって、適した処方は異なります。
薬局やドラッグストアで市販されている漢方薬の中から、自分の状態に最も近いものを見つけることが、症状緩和への第一歩となります。
ここでは、代表的な症状別に適した漢方薬を紹介します。
サラサラした鼻水が止まらない方向けの漢方薬
体が冷えて水分代謝が悪くなり、透明で水のようなサラサラした鼻水(寒痰)が絶えず出るタイプには、体を温めて水分バランスを整える漢方薬が適しています。
代表的な処方は、アレルギー性鼻炎でくしゃみや鼻水を伴う場合によく用いられる小青竜湯です。
また、風邪のひきはじめで寒気や肩こりがある場合には葛根湯が選択肢になります。
さらに、体の水分が偏在し、めまいやむくみも見られるようなら、利水作用のある五苓散が用いられることもあります。
これらの漢方薬は、体の冷えを取り除きながら、過剰な水分を排出させることで症状を改善します。
粘り気のある鼻水が喉に張り付く方向けの漢方薬
ネバネバとして粘り気の強い鼻水が喉に絡みつき、不快感が強い場合には、体内の余分な熱や湿を取り除く作用のある漢方薬が用いられます。
副鼻腔炎などで見られるこのような症状には、去痰作用を持つ処方が中心となります。
例えば、辛夷清肺湯(しんいせいはいとう)は、濃く粘り気のある鼻水や鼻づまりを改善する効果が期待できます。
喉の不快感や咳が主な場合は、粘りついた痰を出しやすくする去痰薬としての役割も果たします。
これらの漢方薬は、鼻や喉の炎症を鎮め、粘りついた鼻水を排出しやすくすることで、喉の奥に張り付く不快な症状を和らげます。
鼻づまりや頭重感がつらい方向けの漢方薬
慢性副鼻腔炎(蓄膿症)が原因で後鼻漏が起こり、特に鼻づまりやそれに伴う頭重感がつらい場合には、鼻の通りを良くし、炎症を抑える漢方薬が適しています。
比較的体力があり、鼻詰まりが主症状の方には、葛根湯加川芎辛夷(かっこんとうかせんきゅうしんい)がよく用いられます。
この処方は血行を促進し、鼻粘膜の腫れを鎮める働きがあります。
一方、濃い鼻水が出て熱感を伴うような強い鼻づまりには、辛夷清肺湯(しんいせいはいとう)が選択されます。
これらの漢方薬は、鼻腔内の膿を排出し、炎症を鎮めることで、しつこい鼻づまりや不快な頭重感を改善します。
喉の乾燥や空咳を伴う方向けの漢方薬
後鼻漏に伴い、喉が乾燥してイガイガし、コンコンと乾いた咳(空咳)が出る場合には、体に潤いを与える漢方薬が用いられます。
このような症状は、体の水分が不足している状態と考えられます。
代表的な処方である麦門冬湯は、気道に潤いを与えて粘膜を保護し、切れにくい痰やこみ上げるような咳を鎮める作用があり、気管支炎などにも応用されます。
また、喉の痛みや腫れが顕著な場合は、炎症を和らげる桔梗湯を併用することもあります。
これらの漢方薬は、喉や気管支の乾燥を改善し、粘膜のバリア機能を高めることで、刺激による咳や喉の不快感を和らげます。
黄色く粘っこい鼻水が出る方向けの漢方薬
体内に熱がこもり、細菌感染などを伴う炎症が起きている場合、黄色く粘り気のある鼻水(熱痰)が出ることがあります。
このような後鼻漏には、体の熱を冷まし、炎症を鎮める「清熱作用」のある漢方薬が適しています。
例えば荊芥連翹湯は、慢性鼻炎や扁桃炎、にきびなど、体質的に熱症状が出やすい方の炎症を鎮めるのに用いられます。
また、膿のような鼻水と鼻づまりが強い場合は辛夷清肺湯、咳や色のついた痰が目立つ場合は清肺湯なども選択肢となります。
これらの漢方薬は、体内の過剰な熱を取り除き、化膿性の炎症を抑えることで症状を改善します。
後鼻漏の漢方薬を選ぶ際のポイント
市販の漢方薬を試す際には、まず自分の症状や体質に合っているかを確認することが大切です。
添付文書をよく読み、用法・用量を守って服用を開始しましょう。
一般的に、2週間程度服用を続けても症状の改善が見られない、あるいは吐き気などの副作用が現れた場合は、服用を中止して医師や薬剤師に相談が必要です。
後鼻漏は慢性化しやすい症状でもあるため、自己判断で長期間服用を続けることは避け、専門家のアドバイスを受けることが望ましいです。
市販薬と病院で処方される漢方薬の違い
ドラッグストアなどで手に入る市販薬と、医療機関で医師から処方される医療用漢方薬には、いくつかの違いが存在します。
市販薬は、多くの人が安全に使えるように、医療用に比べて有効成分の配合量が調整されている場合があります。
そして、漢方専門の薬局でお茶のように煎じて服用する煎じ薬は、
多くは自費ですが、よりオーダーメイド的に漢方薬の調整が可能です。
一方、医療用漢方薬は医師の診断に基づき、保険適応が可能です。
市販薬は手軽に試せるメリットがありますが、症状が重い場合や改善しない場合は、漢方に明るい医療機関を受診する方が適切な治療につながります。
自分の体質に合う漢方薬を見つけるための相談先
後鼻漏の症状は多様であり、自分に最適な漢方薬を見つけるためには専門家への相談が有効です。
まずはドラッグストアや薬局にいる薬剤師、または登録販売者に相談するのが手軽な方法です。
より詳しいアドバイスが必要な場合は、漢方に精通した医師がいるクリニックや、漢方専門の薬局を選ぶと良いでしょう。
特に漢方専門薬局では、時間をかけたカウンセリングを通じて、症状だけでなく生活習慣や体質全体を把握した上で、最適な漢方薬を提案してくれます。
東京に限らず、「漢方 ◯◯(地域名)」などでインターネット検索してみると、専門の相談窓口も多く、まずは近くの店舗を探してみるのも一つの手段です。
漢方と合わせて試したい後鼻漏のセルフケア
後鼻漏の症状を和らげるためには、漢方薬の服用だけでなく、日々のセルフケアを組み合わせることが効果的です。
特に空気が乾燥する冬や、体が冷えやすい夜は症状が悪化しやすいため、生活習慣の見直しが求められます。
体を温め、鼻や喉の潤いを保つための食事、鼻のケア、睡眠の質を高める工夫などを取り入れることで、漢方薬の効果を助け、根本的な体質改善を促進します。
体を温めて血行を促進する食生活
後鼻漏の改善には、体を温めて血行を促進する食生活が役立ちます。
冷たい飲み物や食べ物、生野菜、甘いものの過剰摂取は、体を冷やし胃腸の機能を低下させるため、水分代謝を悪化させる原因となります。
これらを控え、食事にはネギ、ショウガ、シソなどの香味野菜や根菜類を積極的に取り入れるのがおすすめです。
これらの食材は体を温める作用が期待できます。
また、温かいスープや飲み物を日常的に摂ることで、鼻や喉の粘膜を潤し、症状を和らげることにもつながります。
バランスの取れた食事で、胃腸の働きを健やかに保つことが大切です。
鼻うがいで鼻腔内を清潔に保つ
鼻うがいは、鼻腔内に付着したアレルゲンやウイルス、ほこりなどを洗い流し、鼻の中を清潔に保つための効果的なセルフケアです。
鼻腔内の異物を除去することで、粘膜の炎症を抑え、後鼻漏の不快感を軽減する効果が期待されます。
実践する際は、市販の専用キットを使用するか、体温程度のぬるま湯に食塩を溶かした生理食塩水を用意します。
片方の鼻からゆっくりと液体を吸い込み、口から出すのが基本的な方法です。
特に副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎が原因の場合、日常的に行うことで鼻の通りが改善されます。
ただし、誤った方法では耳を痛める可能性があるため、説明書をよく読んで正しく行いましょう。
十分な睡眠で体の抵抗力を高める
睡眠不足は自律神経のバランスを乱し、免疫力を低下させるため、後鼻漏の症状を悪化させる要因になります。
質の高い睡眠を十分にとることは、体の抵抗力を高め、炎症を起こしている鼻や喉の粘膜を修復するために不可欠です。
快適な睡眠環境を整えるため、就寝前のスマートフォンの使用を控え、リラックスできる時間を持つことが推奨されます。
また、寝室の湿度は50~60%程度に保つのが理想的です。
加湿器などを利用して乾燥を防ぐと、夜間の喉のイガイガ感や咳を和らげることができます。
規則正しい生活を送り、心身の疲労をしっかり回復させましょう。
まとめ
後鼻漏は、鼻水が喉に垂れる不快な症状で、アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎など多様な原因によって引き起こされます。
漢方治療は、症状そのものに対処するだけでなく、体質にある「冷え」や「水滞」といった根本原因にアプローチする方法です。
市販の漢方薬を選ぶ際は、鼻水がサラサラかネバネバか、色やその他の症状を確認し、小青竜湯や辛夷清肺湯といった処方から自分に合ったものを見つけます。
漢方薬の服用に加え、体を温める食事や鼻うがい、十分な睡眠などのセルフケアを併用すると、より効果的です。
症状が長引く場合や、どの薬を選べばよいか迷う際は、医師や薬剤師などの専門家に相談してください。