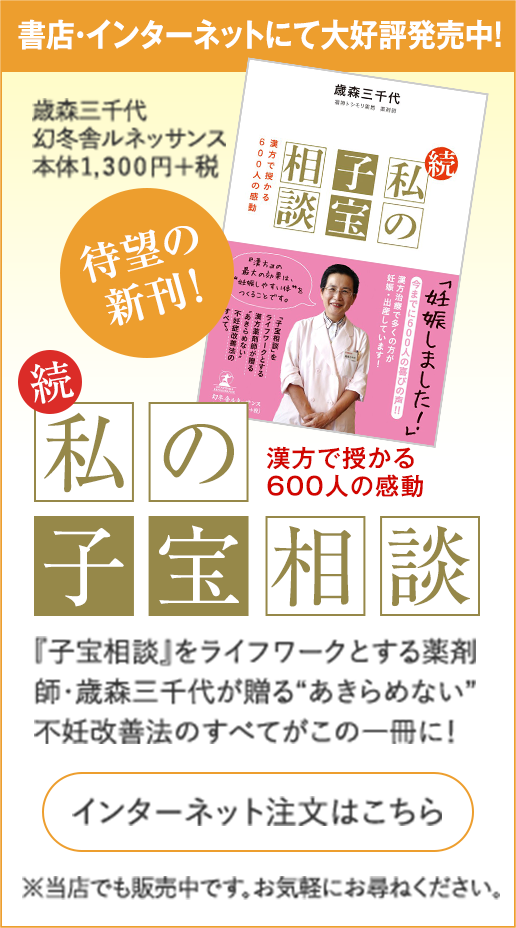坐骨神経痛にオススメの漢方薬は?市販で買えるおすすめと効果を解説
 漢方
漢方
坐骨神経痛によるつらい痛みやしびれを和らげるため、市販の漢方薬を試したいと考える方は少なくありません。
漢方薬は、西洋薬とは異なるアプローチで体質から改善を目指す薬です。
このブログ記事では、坐骨神経痛に良いとされる漢方薬について、その効果や選び方を解説します。
症状や体質に合ったおすすめの市販薬を知り、セルフケアの一環として正しく活用するための情報を紹介します。
そもそも坐骨神経痛とは?主な症状と原因を解説
坐骨神経痛とは、病気の名前ではなく、お尻から太ももの裏、ふくらはぎ、足先にかけて伸びる「坐骨神経」が何らかの原因で圧迫されたり刺激されたりして生じる症状の総称です。
主な症状として、痛みやピリピリとしたしびれ、張り、締め付けられるような感覚などが挙げられます。
この症状を引き起こす代表的な原因疾患には、椎間板が飛び出して神経を圧迫する「腰椎椎間板ヘルニア」や、神経の通り道である脊柱管が狭くなる「腰部脊柱管狭窄症」があります。
多くの場合、腰痛に引き続いて発症しますが、腰に痛みがなくてもお尻や足だけに症状が現れることもあります。
坐骨神経痛への漢方薬のアプローチとは?
漢方医学では、坐骨神経痛のような痛みやしびれは、生命エネルギーである「気」、血液とその働きを指す「血」、血液以外の体液である「水」の巡りが滞ったり、不足したりすることで生じると考えます。
そのため、漢方薬による治療は、単に痛みを抑えるだけでなく、なぜ痛みが生じているのかという根本原因に注目します。
体を温めて血行を促進したり、滞った気や水の流れをスムーズにしたり、加齢などによって衰えた機能を補ったりすることで、体全体のバランスを整え、症状を改善に導くことを目指します。
西洋薬との作用の違いを比較
坐骨神経痛に対して、西洋薬では炎症を抑えたり痛みの信号を遮断したりする非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)などの痛み止めが主に使用されます。
これは、今ある痛みを直接取り除く対症療法です。
今ある辛い痛みにすぐに対処できることは、とても価値がありますが、痛みを起こしている原因にアプローチするという視点を持つことも大切です。
一方、漢方薬は、痛みが生じている体の状態そのものに働きかけます。
例えば、体が冷えて血行が悪くなっている場合には体を温める生薬を、体内の水分が滞ってむくみが生じている場合には水分代謝を促す生薬を配合した漢方薬を用います。
このように、漢方薬は痛みの根本原因となっている体質を改善することで、症状を和らげていくという点で、西洋薬とは作用のアプローチが異なります。
【症状・体質別】坐骨神経痛におすすめの市販漢方薬を紹介
坐骨神経痛に用いられる漢方薬は一つではなく、その人の体力や体質、症状の現れ方によって適した薬が異なります。
漢方では、この個々の状態を「証(しょう)」と呼び、証に合った漢方薬を選ぶことが重要です。
ここでは、処方箋なしで、漢方薬局やドラッグストアなどで購入できる市販の漢方薬の中から、坐骨神経痛でよく使われる代表的なものを、それぞれの特徴的な症状や体質別に紹介します。
冷えや足腰の衰えを感じる方には「牛車腎気丸(ごしゃじんきがん)」
牛車腎気丸は、特に高齢者や疲れやすく体力があまりない方に適した漢方薬です。
体が冷えやすく、手足が冷たい、腰や膝に力が入らない、夜間に何度もトイレに起きる、足がむくむといった症状を伴う腰痛やしびれに用いられます。
漢方医学で生命力の源と考える「腎(じん)」の働きが衰えた状態(腎虚)を補い、体を温めながら水分代謝を整えることで、足腰の痛みやしびれ、排尿トラブルなどを改善します。
加齢による足腰の衰えが気になる方の坐骨神経痛に適しており、冷えが症状を悪化させる場合に効果が期待できます。
痛みやしびれで血行不良が気になる方には「疎経活血湯(そけいかっけつとう)」
疎経活血湯は、血行不良が原因で起こる痛みやしびれに用いられる漢方薬です。
漢方では、血の流れが滞った状態を「瘀血(おけつ)」と呼び、痛みの原因の一つと考えます。
疎経活血湯は、滞った「気」と「血」の流れをスムーズにし、体内の余分な水分を取り除くことで、関節痛や神経痛、筋肉痛を和らげます。
特に、筋肉のこわばりを伴う痛みや、同じ場所が繰り返し痛むような場合に適しています。
体力が中等度の方で、痛みやしびれが主な悩みである場合に選択肢となる処方です。
足がつるような急な痛みが特徴なら「芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう)」
芍薬甘草湯は、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みに効果を発揮する漢方薬で、「こむら返り」の特効薬として知られています。
坐骨神経痛においても、ふくらはぎなどが急につって激しく痛む場合に有効です。
筋肉の緊張を緩め、痛みを鎮める作用があり、比較的即効性が期待できるのが特徴です。
そのため、体質改善を目的として長期間服用する他の漢方薬とは異なり、痛みやけいれんが起きたときに頓服薬として使用されることが一般的です。
就寝中に足がつって目が覚めてしまうような方にも適しています。
冷えと体力の低下による関節痛には「桂枝加朮附湯(けいしかじゅつぶとう)」
桂枝加朮附湯は、体力がなく、冷え性で汗をかきやすい方の関節痛や神経痛に用いられる漢方薬です。
体を温める作用が強く、特に寒さや湿気によって症状が悪化するタイプの痛みに適しています。
冷えると痛みが増す、手足が冷たくて動かしにくい、といった症状を伴う坐骨神経痛の方に効果が期待できます。
比較的体力が低下している方向けの漢方薬です。
冷えが原因の腰痛や神経痛には「五積散(ごしゃくさん)」
五積散は、冷えによって「気・血・水」の流れがすべて滞ることで生じる様々な不調に対応する漢方薬です。
体が冷えて血行が悪くなり、さらに余分な水分が溜まることで起こる腰痛や神経痛、関節痛などに用いられます。
特に、夏場の冷房などで体が冷え切ってしまった時や、寒くて湿度の高い日に症状が悪化する方に適しています。
体を温め、発汗を促し、水分代謝を整えることで痛みを和らげるほか、胃腸の不調や頭痛、肩こりなど、冷えに伴う複合的な症状にも効果が期待できます。
夜間の頻尿やむくみを伴う腰痛には「八味地黄丸(はちみじおうがん)」
八味地黄丸は、加齢に伴う体の機能低下(腎虚)を補う代表的な漢方薬です。
疲れやすくだるさを感じ、手足が冷えやすい一方で、口の渇きを感じることもあります。
坐骨神経痛の症状としては、腰痛のほかに、足のしびれ、夜間の頻尿、排尿困難、足のむくみなどを伴う場合に適しています。
体を温め、全身に栄養と潤いを与えることで、足腰の衰えや痛み、泌尿器系のトラブルを改善します。
特に、中高年以降や更年期における腰痛や下半身の諸症状に効果が期待できる漢方薬です。
市販の漢方薬を試す前に知っておきたい3つの注意点
市販の漢方薬は、処方箋が要らず、漢方薬局やドラッグストアなどで手軽に入手でき、セルフケアの選択肢として有用です。
しかし、医薬品である以上、その使用には注意が必要です。
効果を正しく得て、安全に服用するために、事前に知っておくべきポイントがあります。
ここでは、漢方薬を試す前に押さえておきたい3つの注意点を解説します。
自己判断せず薬剤師や登録販売者に相談する
漢方薬はその人の体質や体力、症状の現れ方などを総合的に判断する「証」に合わせて選ぶことが最も重要です。
同じ坐骨神経痛という症状でも、体が冷えている人、血行が悪い人、体力が落ちている人では、適した漢方薬が異なります。
自分の「証」に合わない薬を選んでしまうと、十分な効果が得られないだけでなく、かえって体調を崩してしまう可能性もあります。
購入する際には自己判断で選ばず、店舗などにいる薬剤師や登録販売者に、具体的な症状や体質を詳しく伝え、専門家のアドバイスを受けて最適な漢方薬を選ぶようにしてください。
用法・用量を守って正しく服用する
漢方薬は、定められた用法・用量を守って服用することで、本来の効果を発揮します。
多くの漢方薬は、胃の中に食べ物が入っていない空腹時に服用するのが効果的とされるため、食前(食事の30分~1時間前)や食間(食事と食事の間、食後2時間程度)に服用するよう指示されています。
お湯に溶かして飲むと、香りが立って吸収も良くなると言われています。
飲み忘れたからといって、2回分を一度に服用することは避けてください。
製品のパッケージや説明書をよく読み、記載された指示に従って正しく服用を続けることが大切です。
体調に異変があればすぐに服用を中止する
漢方薬は天然の生薬から作られていますが、医薬品であり、副作用が起こる可能性はゼロではありません。
体質に合わなかった場合、食欲不振や胃のむかつき、吐き気といった消化器症状や、発疹、かゆみなどの皮膚症状が現れることがあります。
また、まれに重篤な副作用として、間質性肺炎や肝機能障害、偽アルドステロン症などが起こることもあります。
服用を始めてから、いつもと違う気になる症状が現れたり、体調に異変を感じたりした場合は、直ちに服用を中止し、購入した薬局の薬剤師や医師、または販売者に相談してください。
漢方薬を試しても改善しない場合は病院へ
市販の漢方薬を一定期間試しても症状が軽くならない、あるいは悪化する場合には、セルフケアの範囲を超えている可能性があります。
また、坐骨神経痛の症状の中には、緊急の対応を要する危険なサインも存在します。
そのような場合は、自己判断で様子を見続けず、速やかに整形外科などの医療機関を受診することが重要です。
痛みが激しく日常生活に支障が出ているとき
じっとしていても痛みが治まらない、痛みで夜も眠れない、歩くのがつらいなど、痛みが非常に強く、日常生活に深刻な支障が出ている場合は、市販薬で対応できるレベルを超えていると考えられます。
神経の圧迫が強い可能性や、他の重篤な疾患が隠れている可能性も否定できません。
痛みを我慢し続けると、症状が慢性化したり、原因となっている疾患が悪化したりする恐れがあります。
まずは専門医による正確な診断を受け、適切な治療方針を立ててもらうことが必要です。
足に力が入らない・感覚がないとき
足首や足の指に力が入らず、持ち上げられない(下垂足)、スリッパが意図せず脱げてしまう、何もないところでつまずきやすい、といった筋力低下の症状は、神経が強く圧迫されていることを示す危険なサインです。
また、太ももの裏やふくらはぎ、足の裏などを触っても感覚が鈍い、しびれが強くて触られている感じがしない、といった知覚障害も同様です。
これらの症状は、神経の機能が著しく低下している状態で、放置すると麻痺が後遺症として残る可能性があるため、直ちに整形外科を受診してください。
排尿・排便に障害があるとき
坐骨神経痛に伴って、尿が出にくい、逆に尿意を我慢できず漏らしてしまう、便秘がひどくなった、といった排尿・排便に関する異常が現れた場合、これは最も緊急性の高い症状です。
膀胱や直腸の働きをコントロールしている「馬尾神経」が強く圧迫されている可能性があり、「馬尾症候群」と呼ばれます。
この状態を放置すると、恒久的な機能障害につながる危険性が非常に高いため、症状に気づいたら時間をおかずに、すぐに救急外来を受診するなど、迅速な対応が必要です。
坐骨神経痛と漢方薬に関するQ&A
ここでは、坐骨神経痛の改善のために漢方薬の服用を検討している方が抱きやすい疑問について、Q&A形式で解説します。
効果を実感できるまでの期間や副作用の有無、医療機関で処方される薬との違いなど、気になるポイントを整理して、不安や疑問の解消に役立ててください。
漢方薬はどのくらいで効果が出ますか?
漢方薬の効果が現れるまでの期間は、薬の種類や個人の体質、症状の重さによって大きく異なります。
「芍薬甘草湯」のように、筋肉のけいれんに対して比較的すぐに効果が期待できるものもありますが、多くの漢方薬は体質からじっくりと改善していくため、効果を実感するまでには時間がかかることが一般的です。
まずは2週間から1ヶ月程度を目安に服用を続けてみることが推奨されます。
もし1ヶ月ほど服用しても症状に変化が見られない場合は、薬が体質に合っていない可能性も考えられるため、医師や薬剤師に相談してください。
副作用はありますか?
漢方薬は天然由来の生薬で構成されているため、安全なイメージがありますが、医薬品である以上、副作用のリスクは存在します。
体質に合わないものを服用すると、胃もたれや食欲不振、下痢などの消化器症状や、発疹、かゆみといった皮膚症状が出ることがあります。
また、特定の生薬(例えば甘草)の過剰摂取による偽アルドステロン症(むくみ、血圧上昇など)や、まれに肝機能障害、間質性肺炎といった重篤な副作用が起こる可能性も報告されています。
体調に異変を感じた場合は、すぐに服用を中止して専門家に相談することが重要です。
病院で処方される漢方薬と市販薬の違いは何ですか?
病院で処方される医療用漢方製剤とドラッグストアなどで購入できる一般用漢方製剤(市販薬)の主な違いは、有効成分である生薬の含有量と健康保険適用の有無です。
漢方薬には、たくさんの種類があり、保険適応になっていない漢方薬も多く存在します。
クラシエやツムラといったメーカーは、医療用と市販薬の両方を製造しています。
医療用は医師の診断に基づいて処方され、健康保険が適用されますが、市販薬は自己の判断で購入し、費用は全額自己負担となります。
まとめ
坐骨神経痛の症状緩和には、市販の漢方薬も選択肢の一つです。
漢方薬は痛みやしびれの原因となる体質に着目し、冷えや血行不良、体力の低下などを改善することで症状にアプローチします。
牛車腎気丸や疎経活血湯など、様々な種類があるため、自分の症状や体質に合ったものを選ぶことが重要です。
購入の際は、薬剤師や登録販売者などの専門家に相談し、用法・用量を守って正しく服用してください。
もし一定期間試しても改善が見られない場合や、筋力低下、排尿障害といった危険な症状が現れた場合は、速やかに医療機関を受診することが必要です。