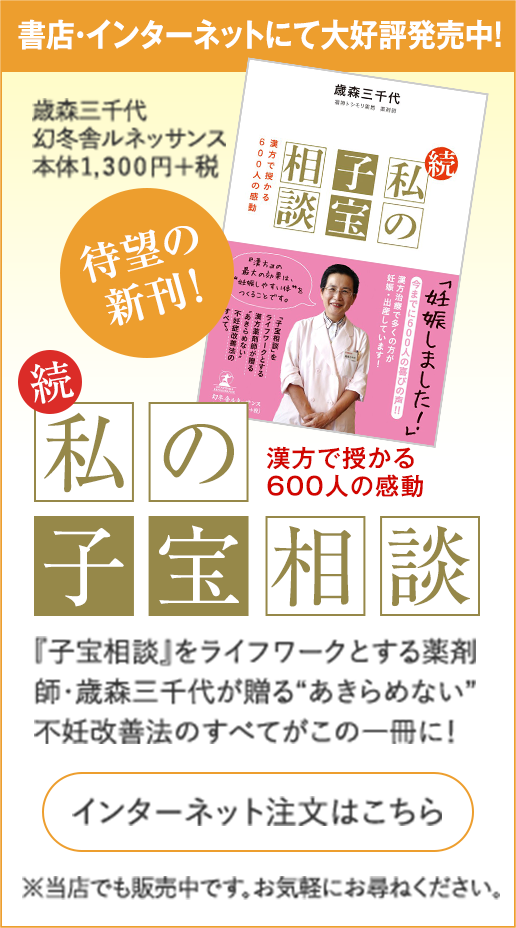高齢不妊の治療は何歳まで?出産リスクと成功率を上げる方法
 妊活・不妊
妊活・不妊
年齢を重ねてからの妊活では、妊娠や出産に対する不安を感じることが少なくありません。
実際に、女性の年齢は妊娠のしやすさに大きく影響し、高齢になるほど不妊のリスクは高まります。
この記事では、年齢が妊娠・出産に与える具体的な影響や、高齢不妊の治療における年齢の考え方、そして妊娠の成功率を上げるための具体的な方法について解説します。
医学的な事実を理解し、適切な治療や対策を検討するための一助としてください。
不妊治療に年齢制限はある?知っておきたいタイムリミット
不妊治療に医学的な年齢制限は設けられていませんが、妊娠率の観点から事実上のタイムリミットは存在します。
一般的に30代後半から妊娠率は緩やかに低下し始め、40歳を超えるとさらにその傾向は顕著になります。
体外受精においても、38歳での出産率は約20%ですが、40歳では約10%に低下し、43歳では5%未満となるデータもあります。
そのため、多くのクリニックでは43歳から45歳あたりを治療終了の一つの目安としています。
38歳から治療を開始して5年後に終えるケースも考慮すると、早期の決断が求められます。
年齢を重ねると妊娠率が低下する医学的な理由
なぜ年齢が上がると妊娠しにくくなるのでしょうか。
その最も大きな原因は、女性の加齢に伴う「卵子の質の低下」と「卵子の数の減少」にあります。
女性が持つ卵子は生まれつき数が決まっており、年齢とともに新しく作られることはありません。
そのため、体と同じように卵子も老化していきます。
また、子宮筋腫などの婦人科系疾患のリスクが上がることも一因です。
不妊の原因は男性側にある場合も約半数を占めるため、女性だけの問題ではないことも理解しておく必要があります。
卵子の質が下がり染色体異常の割合が高まる
女性の卵子は胎児の時に作られ、その後新しく作られることはないため、年齢とともに卵子も老化します。
卵子の老化で特に問題となるのが、細胞のエネルギー産生を担うミトコンドリアの機能低下です。
ミトコンドリアの働きが衰えると、卵子が成熟し分裂する過程で染色体を正常に分配する力が弱まり、染色体異常の発生率が高まります。
染色体異常を持つ受精卵は、着床しにくい、着床しても成長が途中で止まってしまう、あるいは流産に至る可能性が高くなります。
これが、加齢によって妊娠率が低下し、流産率が上昇する大きな要因です。
加齢とともに体内の卵子の数は減少していく
女性が生まれ持った卵子の数は生涯で増えることはなく、年齢と共に減少し続けます。
出生時には約200万個ある原子卵胞は、初経を迎える頃には約30万個にまで減少し、その後も毎月の排卵だけでなく、自然に消滅していくことでその数を減らしていきます。
特に30歳を過ぎたあたりから減少のスピードは加速し、32歳、36歳と年齢を重ねるごとにそのペースは速まります。
37歳頃には約2万5千個まで減少するといわれ、卵子の数が少なくなることは、妊娠の機会そのものが減っていくことを意味します。
この卵子の在庫の減少が、加齢による妊娠率低下の直接的な原因の一つです。
子宮筋腫といった婦人科系疾患のリスクが上がる
年齢を重ねると、子宮筋腫や子宮内膜症、子宮腺筋症といった婦人科系の疾患にかかるリスクも高まります。
これらの疾患は、それ自体が不妊の原因となる可能性があります。
例えば、子宮筋腫ができる位置や大きさによっては、受精卵の着床を妨げたり、子宮の形を変形させて妊娠の継続を困難にしたりすることがあります。
また、子宮内膜症は卵巣や卵管の周囲に癒着を起こし、排卵や卵子のピックアップを阻害する要因となります。
これらの疾患は妊娠後の合併症リスクを高めることにもつながるため、不妊治療を開始する前や治療中に、婦人科検診で子宮や卵巣の状態を正確に把握しておくことが不可欠です。
高齢出産で考えられる母体と赤ちゃんへの影響
高齢での妊娠は、妊娠率の低下だけでなく、妊娠が成立した後の出産に至るまでの過程にも様々な影響を及ぼします。
母体においては、流産のリスクが高まるほか、妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病といった合併症を発症しやすくなります。
一方、赤ちゃんにとっても、母体の年齢が上がるにつれて染色体異常の発生頻度が高まることが知られています。
これらのリスクを正しく理解し、妊娠中から出産後まで、慎重な健康管理と適切な医療的サポートを受けることが求められます。
流産や妊娠高血圧症候群など母体のリスク
高齢妊娠では、母体にかかる負担が大きくなり、様々なリスクが高まります。
最も頻度が高いのが流産で、その確率は35歳で約25%、40歳では40%以上に上昇します。
これは主に卵子の染色体異常が原因とされています。
また、妊娠中に高血圧や蛋白尿が見られる妊娠高血圧症候群や、血糖値が高くなる妊娠糖尿病などの合併症を発症するリスクも年齢とともに増加します。
これらの合併症は、母体の健康を脅かすだけでなく、胎児の発育不全や早産の原因となることもあります。
さらに、前置胎盤や常位胎盤早期剥離といった分娩時の異常や、帝王切開での出産となる割合も高くなる傾向が見られます。
ダウン症候群など赤ちゃんの染色体異数の可能性
母体の年齢が上昇すると、生まれてくる赤ちゃんがダウン症候群(21トリソミー)などの染色体異数性を持つ確率が高まります。
これは、加齢による卵子の質の低下が原因で、卵子の減数分裂の過程で染色体が正しく分配されないエラーが起こりやすくなるためです。
例えば、ダウン症候群の赤ちゃんが生まれる頻度は、母親が25歳で1/1250であるのに対し、35歳では1/385、40歳では1/106と上昇します。
特に40代になるとその確率は顕著に高くなり、45歳では1/30にまで達します。
こうした背景から、高齢妊娠では出生前診断を検討するカップルもいますが、その検査内容や結果の受け止め方について、事前に十分なカウンセリングを受けることが重要です。
高齢でも妊娠の成功率を上げるための具体的な方法
年齢的な要因は変えられませんが、妊娠の成功率を高めるためにできることはあります。
まずは、バランスの良い食事や適度な運動を取り入れ、妊娠しやすい体づくりを目指すことが基本です。
その上で、不妊の原因を特定し、時間を無駄にしないためにも早めに専門医に相談し、適切な治療計画を立てることが求められます。
特に高齢の場合は、タイミング法や人工授精に時間をかけるよりも、体外受精など、より高度な不妊の治療へのステップアップを早期に検討することが有効な手段となり得ます。
バランスの良い食事や適度な運動で体を整える
妊娠に向けた体づくりの基本は、健康的な生活習慣を確立することです。
特に食生活では、特定の食品だけを摂取するのではなく、多様な食材から栄養素をバランス良く摂ることが重要です。
抗酸化作用を持つビタミンCやビタミンEを多く含む野菜や果物、良質なたんぱく質、鉄分などを意識的に摂取することが推奨されます。
また、ウォーキングなどの適度な運動は、全身の血行を促進し、子宮や卵巣の血流改善にもつながります。
ストレスはホルモンバランスを乱す原因となるため、運動を通じて心身をリフレッシュさせることも効果的です。
肥満や痩せすぎは排卵障害のリスクを高めるため、適正体重の維持も心がける必要があります。
早めに治療のステップアップを検討する
年齢が高い場合、不妊治療は時間との勝負になります。
一般的に、避妊せずに性交渉を1年間続けても妊娠しない場合を不妊症と定義しますが、35歳以上ではその期間が半年とされることもあります。
特に40歳を過ぎてからの妊活では、タイミング法や人工授授精といった比較的負担の少ない治療を長期間続けることは推奨されません。
半年から1年程度で結果が出ない場合は、より妊娠率の高い体外受精や顕微授精へのステップアップを積極的に検討すべきです。
2年、3年と時間をかけるのではなく、限られた時間の中で最も可能性の高い方法を選択していくために、治療開始時から医師と将来的な治療方針についてよく話し合っておくことが不可欠です。
将来の妊娠に備える「卵子凍結」という選択肢
将来的に子どもを望むものの、現時点では妊娠が難しいという場合に有効な選択肢が「卵子凍結」です。
これは、若く質の良い状態の卵子を採取して凍結保存し、将来の妊娠に備える医療技術を指します。
卵子の質は年齢とともに低下するため、妊娠率が高いとされる20代後半から30代前半のうちに卵子を保存しておくことで、将来、体外受精を行う際の成功率を高めることが期待できます。
キャリア形成やパートナーがいないといった理由で、今すぐの妊娠を計画していない女性にとって、将来の選択肢を広げるための一つの手段です。
ただし、採卵や凍結保存、そして将来の体外受精には費用がかかり、凍結した卵子が必ずしも妊娠につながるわけではない点も理解しておく必要があります。
不妊治療の保険適用と助成金制度における年齢要件
不妊治療を進める上で、経済的な負担は大きな課題となります。
現在、日本では体外受精や人工授精などの一部の不妊治療に公的医療保険が適用されるようになりました。
しかし、この保険適用制度を利用するには、治療開始時の女性の年齢に上限が設けられています。
また、保険適用外の治療や先進医療に対しては、国や地方自治体が独自に助成金制度を設けている場合があります。
これらの公的支援制度を有効に活用するためには、年齢や回数などの条件を事前に正確に把握しておくことが治療計画を立てる上で重要です。
保険診療で治療を受けられる年齢と回数の上限
2022年4月から、体外受精・顕微授精、人工授精などの基本的な不妊治療が保険適用の対象となりました。
これにより、治療費の自己負担が原則3割に軽減されましたが、この制度には年齢と回数の制限が設けられています。
保険診療を受けられるのは、治療開始時点の女性の年齢が43歳未満の場合に限られます。
また、保険が適用される体外受精の回数は、治療開始時の年齢が40歳未満であれば子ども1人につき通算6回まで、40歳以上43歳未満の場合は通算3回までと定められています。
この回数制限は移植の回数でカウントされるため、治療計画を立てる際には、上限回数を意識した上で進める必要があります。
自治体が独自に設けている助成金制度も確認しよう
国の保険適用制度とは別に、各地方自治体が独自に不妊治療に関する助成金制度を設けている場合があります。
これらの制度は、保険適用外の治療や、先進医療として実施される特定の治療にかかる費用の一部を補助するものです。
助成の対象となる治療内容、所得制限の有無、年齢要件、助成額は自治体によって大きく異なります。
例えば、保険診療と併用した先進医療の費用を助成したり、保険適用の回数上限を超えた後の治療を支援したりするケースがあります。
これらの情報は、居住している市区町村の公式ウェブサイトや保健所の窓口で確認できるため、利用可能な制度がないか事前に調べておくことが経済的負担の軽減につながります。
まとめ
女性の年齢は、妊娠の成立や安全な出産において重要な要素です。
加齢に伴う卵子の質の低下と数の減少は、妊娠率の低下や流産率の上昇に直結します。
また、高齢出産では母体へのリスクや、赤ちゃんが染色体異常を持つ可能性も高まります。
こうした医学的な事実を理解した上で、妊娠の可能性を高めるための対策を講じることが求められます。
具体的には、健康的な生活習慣を基本とし、年齢を考慮して早期に体外受精などの治療へステップアップを検討することが考えられます。
不妊治療の保険適用や助成金制度には年齢要件が定められているため、これらの情報も踏まえ、医師と相談しながら計画的に治療を進める必要があります。